“伝わる”資料作りの基本~実践編~
はじめに:前回のおさらい
前回の記事では、「伝わる資料とは何か?」をテーマに、資料作成の本質や5つのポイントをお伝えしました。
【前回のポイント5つ】
- 「誰に」「何を」伝えるかを明確にする
- 読み手の立場やニーズを意識する
- 1スライド1メッセージを徹底する
- 情報を論理的・構造的に整理する
- シンプルで見やすいデザインにする
これらを押さえることで、見た目だけに頼らない“伝わる資料”の土台ができあがります。
とはいえ、「頭ではわかっていても、実際にどう作ればいいの?」という声も多いのが現実です。そこで本記事では、資料作成が苦手な人でも迷わず進められるように、「資料づくりの実践ステップ」を5段階に分けて、具体的に解説していきます。一つひとつのステップを意識して取り組めば、明日からの仕事で“伝わる資料”が自然と作れるようになるはずです。
この記事はこんな人におすすめ
- 資料作成のポイントはわかっていても、実践になると手が動かない方
- 「相手に伝わる」資料を作成するためのステップが知りたい方
- 毎回デザインばかりに気を取られて、資料作成に毎回時間がかかってしまう方
目次
1. 第1章:実践!伝わる資料の作り方
- 1-1. 目的を決める
- 1-2. 伝えたいこと(伝えるべき事)を考える
- 1-3. 伝え方を考える(全体の構造をつくる)
- 1-4. スライドに落とす
- 1-5. 整える 2. 第2章:資料作成の注意点
- 注意点①
- 注意点②
- 注意点③ 3. 終わりに:今回のポイントのおさらい
- 今回のポイント
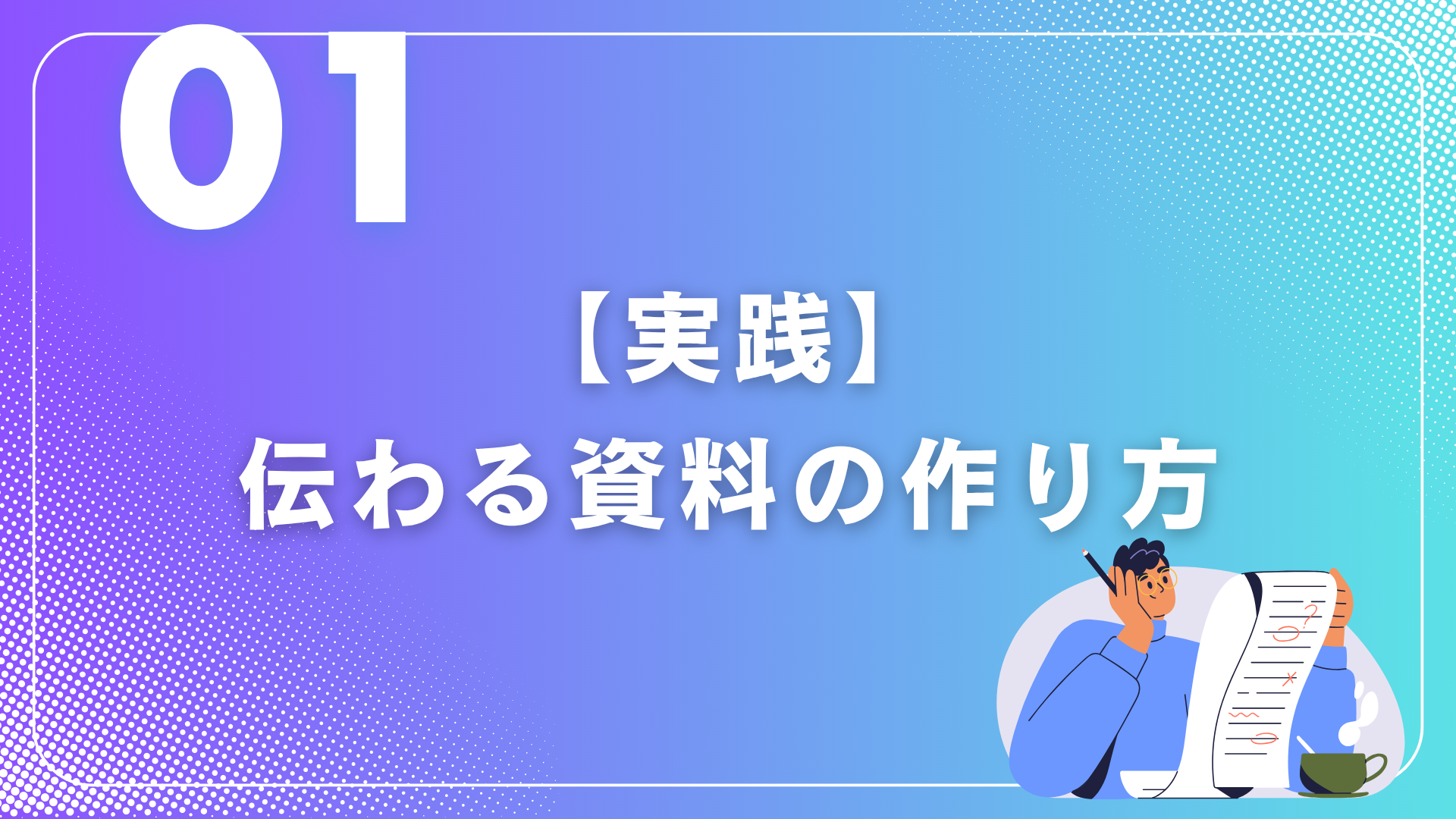
第1章:実践!伝わる資料の作り方
これまで、伝わる資料に共通する5つのポイントをご紹介しました。この章では、資料作成が苦手な人でも迷わず取り組めるように、実際のフローを5ステップに分けて丁寧に解説していきます。
STEP①:資料のゴールを決める
資料作成の第一歩は、スライドを作り始めることではありません。前回の「伝わる資料作成の基本~ポイント編~」でも学んだように、まずは「誰に」「何のために作成するのか」を明確にすることが大切です。
例えば:
- 【誰に】 上司に
- 【目的】 提案を承認してもらい、プロジェクトを進めるため
この最初のステップをあいまいなまま進めてしまうと、途中で「何を伝えたいんだっけ?」と方向性がブレやすくなります。最初に「資料作成の目的(ゴール)」を定めておくことで、資料全体の一貫性が生まれます。簡単なメモでもOKですが、「資料の設計図」になる部分なので丁寧に考えてみてください。
STEP②:伝えたいこと(伝えるべきこと)を考える
目的や相手が明確になったら、次に行うのは、「この資料で何を伝えるべきか」を具体的に洗い出す作業です。このステップでは、いきなりスライドを作るのではなく、中身の材料出しに集中しましょう。
1. 資料全体を通して一番伝えたいことを決める
ここでまずやるべきことは、この資料で最も相手に伝えたい「メインメッセージ」をひとつ決めることです。
たとえば:
- 「この提案を実行すれば、〇〇という課題が解決できます」
- 「この施策を今やるべきです」
- 「この会社には、あなたが求めている環境があります」
この「主張の柱」が決まることで、その後に出す情報や構成もぶれにくくなります。
2. メインメッセージに繋がる中身を洗い出す
次に、そのメッセージを支えるために必要な情報を、箇条書きなどでどんどん書き出していきます。ここでは、情報の順番や構成は気にせず、頭の中にある要素を一度すべて外に出すイメージです。
ヒントになる問いかけ:
- そのメッセージを裏付ける理由は?
- 具体的な事例やデータはあるか?
- 相手が納得しやすい視点は?
- 実行可能性(コスト・手順)はどう伝える?
- 相手が気にしそうなリスクや不安点は?
情報の洗い出しは、資料作りの土台をつくる作業です。次のステップでは、この出した情報を「どう整理して、どう順序立てて見せるか」を考えていきましょう。
STEP③:情報を構造化して整理する
メインメッセージが決まったら、今度はその根拠や補足情報を、ポイント編の記事で紹介したピラミッドストラクチャーを使って整理してみましょう。
たとえば:
- 【結論】 新人研修の形式をオンライン化すべき
- 【理由①】 コストが削減できる
- 【具体例】 昨年の会場費:年間30万円→ゼロに
- 【理由②】 参加率が上がる
- 【具体例】 昨年度:出席率68%→オンライン導入後:92%
- 【理由③】 講師リソースを有効活用できる
- 【具体例】 録画を活用すれば、繰り返し対応が不要
- 【理由①】 コストが削減できる
このように整理することで、伝えるべき内容に抜けや重複がないかを確認でき、話の筋も通りやすくなります。この作業を怠ると、伝えたいメッセ―ジにつながらないような余計な情報が入ってしまったり、メッセージへの根拠がうまく伝わらない資料になったりしてしまうため、必ずピラミッド構造で論理の筋が通っているのかを確認し、無駄なく、わかりやすい資料になるように整理していきましょう。
STEP④:スライドに落とす
ここまでで、「何を伝えるか(メッセージ)」と「どんな順番で伝えるか(構造)」が整理できました。いよいよこの情報をスライドという“見える形”に落とし込む段階です。
スライド作成でまず意識すべきは、「1スライド1メッセージ」。これは資料作りの鉄則です。1枚のスライドで複数のことを伝えようとすると、読み手は「結局何が言いたいの?」と迷ってしまうので、必ずメッセージは絞るようにしてください。
スライド構成の基本イメージ
スライドの中身は、以下のような3層構造を意識すると、読み手が理解しやすくなります:
- メインメッセージ(タイトル)
- スライドで一番伝えたいこと。読み手が最初に見る場所。
- サブメッセージ(タイトル下の補足文)
- メインの説明や前提、背景などの短い文章。なくてもOK。
- 証拠・具体例(スライドのボディ部分)
- メッセージを裏付ける根拠やデータ、図表など。
例:営業提案資料のスライド構成
- タイトル(メイン): この施策で広告コストが30%削減されます
- サブ文: 類似業界で導入され、一定の成果が出ています
- 本文: グラフ+導入実績+コスト比較表
このように整理することで、読み手が「どこを見て」「何を理解すべきか」が明確になり、資料の説得力も高まります。ここでは、まだデザインや見た目にはこだわりすぎなくてOKです。まずはこの「伝え方の型」にそって、スライドを一通り並べていきましょう。次の最終ステップでは、いよいよスライド全体を“伝わる形”に整えていく工程です。
STEP⑤:整える
スライドに必要な情報が入ったら、最後にやるべきは「整える」工程です。ここでいう「整える」とは、見た目をキレイに飾ることではなく、読み手がスムーズに理解できるように仕上げるということです。
デザインは「装飾」ではなく「伝わりやすさ」のためにあります。デザインというと、「おしゃれに」「映えるように」と考えてしまいがちですが、資料におけるデザインの目的は、「読み手に迷わせず、メッセージを伝えること」です。
【資料を整えるための5つのチェックポイント】
- フォント・文字サイズを統一する
- タイトル、本文、補足のフォントサイズを一貫させる
- フォントの種類は1~2種類に絞るのがベスト
- 色を使いすぎない
- ベース色+強調色(2〜3色以内)におさえる
- 強調したい箇所にだけ色を使うと効果的
- 余白をしっかり取る
- 情報が詰まりすぎていると読みにくくなる
- 思い切って“空ける勇気”が、読みやすさにつながる
- 情報の配置を揃える
- 図や文章の位置がバラバラだと、雑に見える
- テキストの左揃え/図とタイトルの上下整列など基本を意識
- 読み手の視線の流れを意識する
- 上から下、左から右へと“自然に読める順番”で並べる
- 矢印・番号・強調などで「見る順番」をナビゲートする
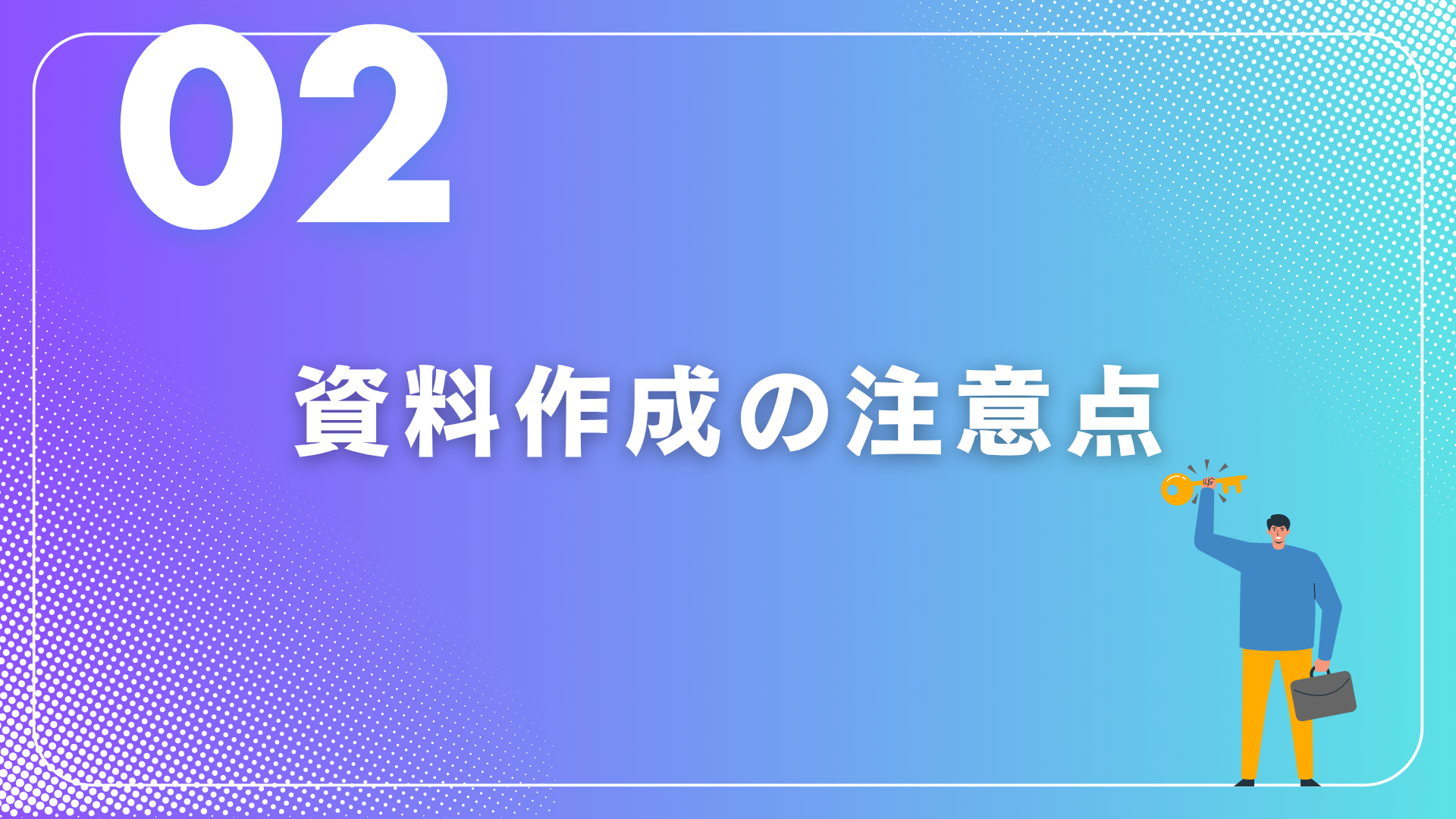
第2章:資料作成の注意点
ここまでで、伝わる資料の作り方とステップはしっかり押さえられました。最後に、実践する中で「よくある落とし穴」を回避するために、資料作成時に意識しておきたい注意点を紹介します。
1. できるだけ早く、相手が知りたいことに到達させる
読み手は、「結局、何が言いたいのか?」を最初に知りたがっています。しかし、よくある落とし穴としては、自分の考えた順番で説明をしてしまうことです。情報を丁寧に並べるよりも、まずは最初に結論を提示することが鉄則です。基本的には、「結論」→「補足情報」の順番でまとめるように意識してみましょう。
2. タイムパフォーマンス(時間対効果)を常に意識する
資料づくりは、時間をかけようと思えばいくらでもこだわれます。しかし、その時間が「成果につながっているか」を常に見直す必要があります。
- この資料は本当に作る必要があるのか?
- 無駄にデザインなどに凝りすぎていないか?
- 想定した時間よりも必要以上に時間をとりすぎていないか?
資料を作成する際にはついつい忘れがちになってしまいますが、タイムパフォーマンスが適切かどうかを常に意識しながら資料作成に臨むようにしましょう。
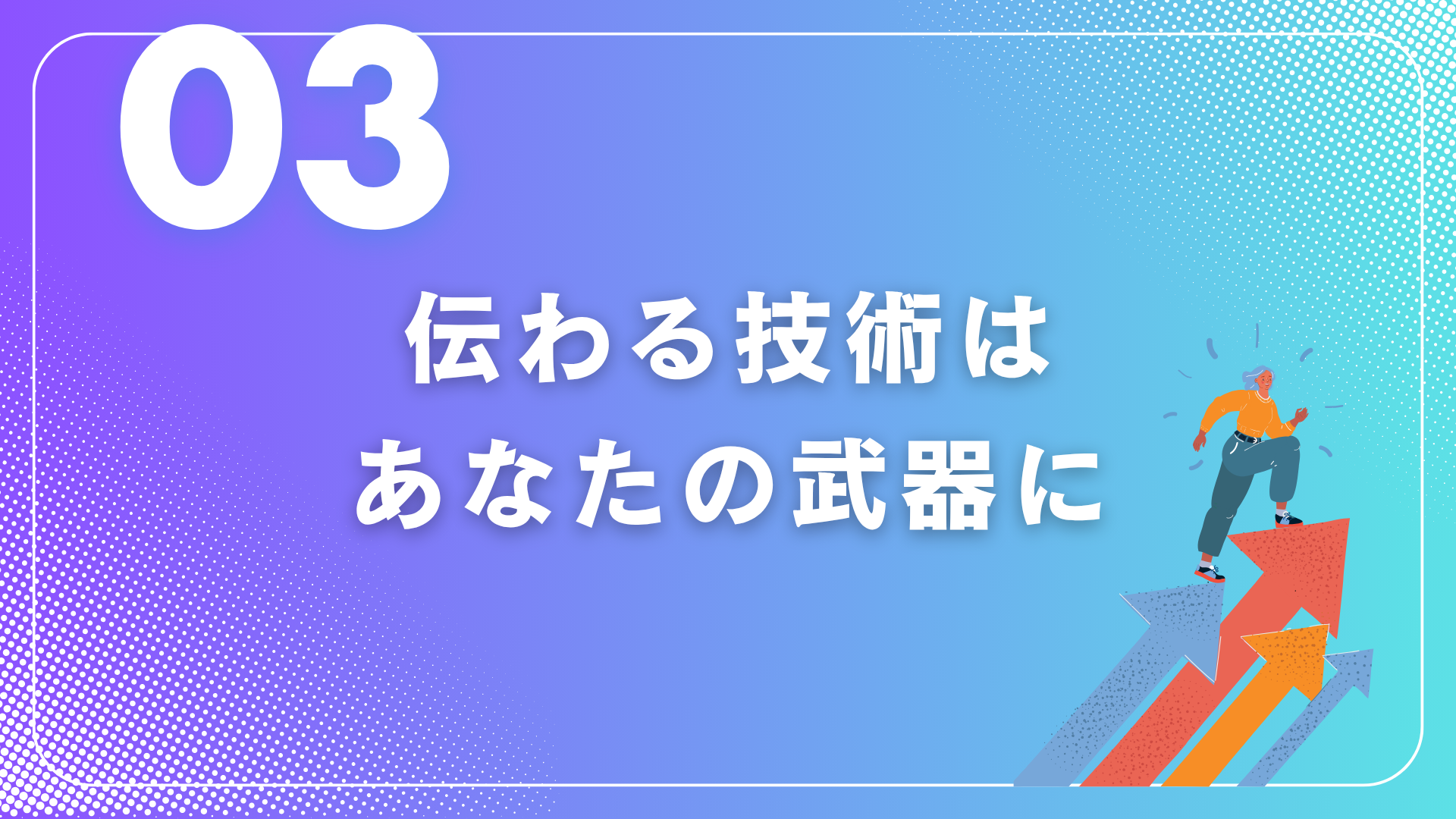
おわりに:伝わる技術は自分の武器になる
実践編では、「伝わる資料」を実際にどのように作っていけばよいのかを、5つのステップに分けて解説してきました。
STEP①でゴールを定め、STEP②で伝えるべき内容を洗い出し、STEP③で情報を論理的に整理する。STEP④でその内容をスライドに落とし込み、最後のSTEP⑤で読み手にとってわかりやすい形に整える。
これらは一見地道な作業に見えるかもしれませんが、実は「伝わる資料」を作るための最短ルートでもあります。
「なんとなく作ってしまう」「見た目だけ整えて満足してしまう」資料は、結局相手に届かず、時間ばかりがかかってしまいがちです。一方で、今回ご紹介したようなステップを意識することで、自分の考えが自然と整理され、読み手にも伝わる資料に仕上がっていきます。
最初はテンプレートのようにこの5ステップをなぞるだけでも、「伝わる確率」は確実に高まります。何より、これらのステップを繰り返すことで、思考の筋道を立てる力や、相手視点でものごとを考える習慣が自然と身につきます。資料はただのアウトプットではなく、「相手に伝える技術」のひとつです。ぜひこの実践ステップを、あなた自身の武器として活用してみてください。

