はじめに:プレゼンは才能?技術?
良いプレゼンとはどのようなプレゼンだと思いますか? 答えはズバリ、“人を動かす”プレゼンです。ビジネスシーンでは相手に何らかの行動を促すことがプレゼンの目的であることが多いでしょう。商談であれば「購入してもらう」、社内提案であれば「承認を得る」といった具体的なアクションを引き出すことがゴールとなるのです。プレゼン後に自身が望む行動を聴き手であるターゲットがとってくれれば、プレゼンは大成功であると言うことができます。
しかし、プレゼンに対して苦手意識を持っている人は多いのではないでしょうか?そもそも人前で話すことが苦手だったり、メッセージを伝えられる資料の作り方がわからなかったり、プレゼンで上司を納得させることなんてもってのほかである、そんな人はきっと多いでしょう。
ですが、安心してください。プレゼンは「才能」ではなく「技術」です。つまり、学び、練習すれば誰でも確実に上達します。本記事ではプレゼンの全体像を 準備→資料作成→実演 の3ステップで分け、それぞれのフェーズで意識すべきポイントを解説していきます。読後にはあなたは“人を動かす”プレゼンができる自信を持てているはずです。
この記事はこんな人におすすめ
- 人前で話すことに苦手意識がある人
- ビジネスシーンでプレゼン機会が多い人
- 相手の心を動かすプレゼンができるようになりたい人

1. プレゼンは準備がなにより大事!
まずはプレゼンの準備を始めましょう。プレゼンで最も重要なのは、実は「話すこと」ではなく、その前段階である「準備」です。準備のフェーズで考えなければならないことは主に3つです。
1. プレゼンの目的を明確にする 2. 聴き手を徹底的に理解する 3. 何を、どう伝えるかを設計する
①プレゼンの目的を明確にする
プレゼンの始まりは「聴き手にどんな行動をとってほしいか」を明確にするところから始まります。プレゼン後のターゲットの行動によってプレゼンが成功であったかどうか判断できます。例えば営業の場であれば「その場で契約を決断してもらう」、社内提案であれば「新規施策を上司に承認してもらう」といった具合です。
さらに重要なのは、「その行動に至るまでのプロセス」を段階的に分解して考えることです。多くの場合、相手の心は以下の順で動きます。
プレゼンを聴く前→ 興味 → 共感 → 納得 → 行動
1回のプレゼンで必ずしも最終行動まで至らなくても、目標の段階まで相手を導ければ成功といえます。
② 聴き手を徹底的に理解する
次に聴き手について理解しましょう。聴き手が複数いる場合は意思決定に影響を及ぼす人間(=ターゲット)は誰か具体的に考え、その人を徹底的に理解することが求められます。
まずはターゲット自身の置かれている状況を確認します。地位、立場、経験、性格、価値観をできる限り把握し、ターゲットに最もふさわしいプレゼン方法を考えます。次にターゲットのプレゼンテーマに関する認識レベルを確認します。プレゼンのテーマに関してどのくらいの興味関心があるのか、またどの程度プレゼン前の前提が把握できているのか確認しておかなければなりません。ターゲットがプレゼンテーマについてほとんど理解がない状態でいきなりテーマを話し始めてもターゲットは何の話をしているのか理解することができないでしょう。最後にターゲットと自分の関係性を確認しておく必要があります。「自分のことをどれくらい知ってくれているのだろうか」、「自分との間に利害関係や力関係はあるのだろうか」、といったことを把握しておき、どんなプレゼンの語り口や構成が効果的か判断しましょう。これらの情報は世の中で公開されている情報を調べてみたり、周囲の人にヒアリングしたりすることで理解していくことができると思います。
③ 何を、どう伝えるのかを設計する
最後にターゲットに何をどう伝えるのかを明確にさせます。まず相手の状況から判断した相手が抱きそうな疑問を洗い出し、絞り込みます。ここでのポイントは相手のすべての疑問に答えることは難しいため、相手の関心が最も強いと考えられる疑問に限定するということです。次にその絞り込んだ疑問に対するメッセージを考え、根拠となる情報を盛り込みます。メッセージは説得力のある根拠が備わってなければなりません。ターゲットに伝えるメッセージが決まったら、次にそのメッセージをどのように伝えるか考えます。ここで大切なポイントが2つあります。
- プレゼンを構成する際になるべく早くターゲットが知りたいことに到達することです。ターゲットは知りたい情報がプレゼン中になかなか出てこないと、退屈になってしまいます。それを防ぐためにもなるべく早くメッセージを明示することは必要です。
- ターゲットの関心が強いところになるべく多くの時間を割くことです。時間をかけて丁寧に説明することでターゲットの関心をさらに強く高めることができます。

2. 聴き手が理解しやすい資料とは?
伝えたいメッセージが定まったら資料作成に移りましょう。(本記事ではパワーポイントでプレゼンを作成することを前提とします。)プレゼン資料を作成するうえで意識することは主に3つです。
① 1スライド1メッセージ
1スライド1メッセージは相手の注意を集中させるために重要です。1スライド1メッセージにすることでスライドごとに伝えたいことが明確になり、聴き手は話の流れを整理しやすくなり、理解が深まります。
② 離れた場所からでも見て伝わる設計
会場の規模によっては聴き手が遠く離れることもあるため視覚的に見やすいスライド構成は意識しなければなりません。具体的には文字の大きさや余白・行間をうまく利用すること、そして伝えたいところは太さや色で強調するなどして、メッセージが伝わるように工夫しましょう。
③ メッセージを際立たせるレイアウト
「何を伝えたいか」が一目でわかるようにメッセージはスライド内で最も目立つ場所に配置しましょう。せっかく伝えたいメッセージを定めていても、印象に残らない配置になっていては伝わりません。また装飾的な画像や無関係なグラフは思い切って削除する勇気も必要です。

3. 実践―心を動かすための伝え方―
最後に実践です。実践の際に抑えるべきポイントは2つあります。立ち居振る舞いと話し方です。
① 立ち居振る舞いのポイント
①-1 アイコンタクト
聴き手の目を見て語り掛けることはとても大切なことです。スライドのほうばかりに視線をやったり、会場をきょろきょろと見渡したりしていると、聴き手は「自分に話しているのかな?」というような疑問を持ってしまいます。アイコンタクトは1人当たり2~3秒目を見ることが理想とされています。
①-2 姿勢
姿勢で大切なのは体重を両足均等にかけて立って背筋をきちんと伸ばすことです。猫背だと相手に暗い印象を与えてしまいますし、体重をかけている足を交互に変えてしまうと、落ち着きのない印象を与えてしまいます。頭の頂点を天井から糸でつるされているという意識を持つと良いかもしれません。
①-3 不要な動作を避ける
話しているときに無意識に持っているペンをいじってしまったり、紙を丸めてしまったりというようなことはないでしょうか。話すときは両手を横に自然に垂らして動かさないか、もしくはおなかの前あたりに両手を持っていく姿勢が良いとされています。
以上で述べた悪い癖は無自覚で行っているケースがほとんどです。したがって改善していくのが難しいですが、動画撮影をしてみて、自身の動きをチェックすることが有効になります。またこれらの悪い癖は自信のなさという気持ちの部分からくるものが多いです。したがって自信を持つことが何より大切であり、自信を持つためにも徹底的に準備、練習することが大切なのです。
② 話し方のポイント
最後にプレゼンで意識すべき話し方について解説します。プレゼンにおいて意識すべき話し方のポイントをご紹介します。
②-1 ひげ言葉を減らす
ひげ言葉は話の間に挟まれる「えー」や「あのー」などの合いの手のように挟まる言葉のことです。話している途中でつい言ってしまう方が多いのではないでしょうか?ひげ言葉は話し手の自信のなさの表れになります。
②-2 語尾まではっきり発音する
途中までハキハキしゃべっていても語尾になって急に曖昧になってしまう人は実は結構いるのです。語尾まで鮮明に話すことを意識することによって聴き手が理解しやすいだけでなく、自信を持っているという印象を与えることができます。
②-3 間を効果的に使う
つい一本調子の同じスピードで話してしまいがちになりますが、大切なことをいう直前や重要なことを言った後に間を開ける ことで聴き手に印象が残りやすいほか、続きがもっと聞きたくなるように聴き手を仕向けることができるのです。
以上話し方で気を付けるべきポイント3つを意識して話せるようになるには心、気持ちの余裕が必要です。余裕がないゆえに「えー」と言葉を探してしまったり、語尾をはっきり言うことができなかったり、間を開けずに一気に話してしまおうとなってしまうのです。心、気持ちの余裕を持つためにもこれから自分が話すことがしっかり理解できている、話す順番が頭の中にしっかり入っている、聴き手からくる質問が想定できている、とプレゼン前に思えているかが最重要なのです。口酸っぱくなりますが、練習を重ねて自信をつけておくことが何より大切なのです。
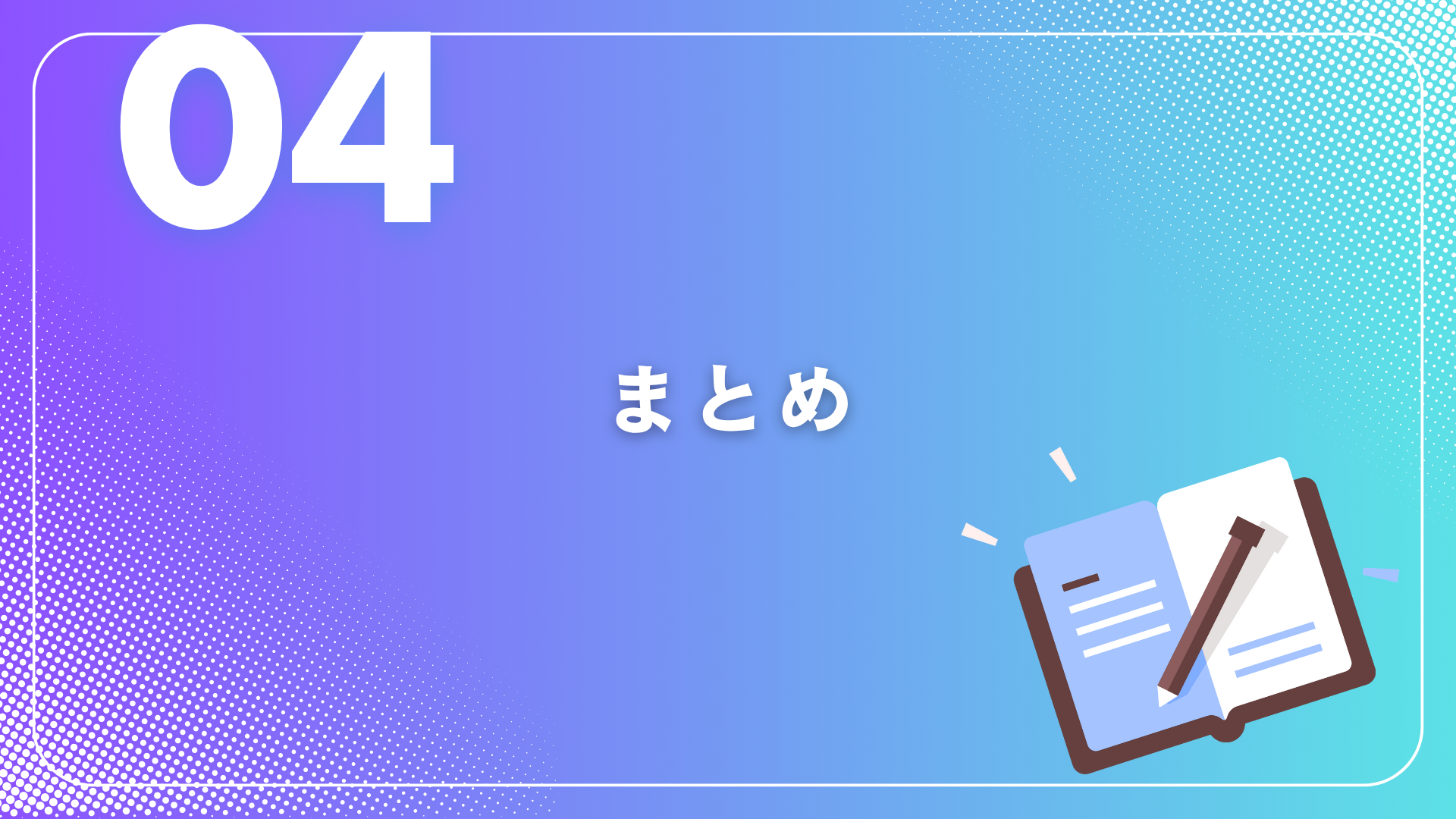
4. まとめ―プレゼンは相手を理解し、行動へと導く技術―
プレゼンは単なる情報の発表ではありません。相手に理解してもらい、納得してもらい、そして行動してもらう――そのための戦略的なコミュニケーションです。だからこそ、最初にすべきは「自分が伝えたいこと」をまとめることではなく、「相手にどう動いてほしいのか」を明確にすることから始まります。目的が定まれば、相手の状況や関心を読み解き、どのように情報を届けるべきかという設計が可能になります。
また、資料作成は単なるビジュアル作業ではなく、相手の理解を助け、メッセージを印象づけるための設計図づくりです。聴き手に配慮した構成は、聞き手の集中力と納得感を高め、プレゼン全体の説得力を飛躍的に向上させます。
そして実演の場面では、話し方や立ち居振る舞いといった“非言語の要素”が思いのほか大きな影響を持ちます。いかに準備を整え、どれだけ自信を持って臨めるか――その心の状態が、言葉の説得力や聞き手の反応に直結するのです。つまり、プレゼンとは「話す内容」だけでなく、「どう届けるか」までを含めた総合的な技術だと言えるでしょう。
プレゼンに苦手意識がある人ほど、正しいステップを踏めば飛躍的な成長を遂げられます。本記事で紹介した考え方と技術を繰り返し実践することで、誰もが「人を動かすプレゼンター」へと近づいていけるはずです!

