はじめに
~ビジネスにおけるアサーティブコミュニケーション~
「言いたいことがあるのに上手く伝えられなかった…」 そんなもどかしさを感じたことはありませんか?伝えたい気持ちはあるのに、うまく言葉にできずに誤解されたり、逆に強く言いすぎてしまったり…。そんな“惜しい伝え方”が、ビジネスシーンでは意外と多いものです。
本記事では、「自己主張」と「優しさ」を両立する伝え方=アサーティブコミュニケーションをテーマに、言葉選びのコツをわかりやすく紹介します。
この記事はこんな人におすすめ
- 自分の話が一度で相手に伝わらなかったことがある方
- 人の意見を尊重しすぎるあまり自分を後回しにしてしまう方
- 交渉や説得に難しさを感じている方
1. アサーティブコミュニケーションとは
アサーティブなコミュニケーションとは、単に自分の意見を主張するのではなく、相手の価値観の違いを前提に尊重しつつ、自分の考えもきちんと伝えるコミュニケーション手法です。最終的な目標は、お互いが率直に話し合える関係を築くことにあります。
当記事では、ビジネスシーンにおいてアサーティブコミュニケーションを用い、相手の気持ちに配慮しながら、自分の考えをしっかり伝えるにはどうすればよいのか。自己主張と思いやりを両立させる言葉の選び方について 解説していきます。
1-1. なぜアサーティブコミュニケーションが必要なのか?
近年、コミュニケーションが難しいと感じることが多くなった思いませんか。コミュニケーションの取り方を間違えれば、リスクになるほど、ものの言い方や伝え方が人や社会に影響力を与える時代になってきています。
価値観や働き方の多様化により、コミュニケーションや意思決定に齟齬が生じ、対人関係でもストレスを招いてしまうといった問題が起きがちです。アサーティブコミュニケーションを身につけることで、以下のような多くのメリットがあります。
- コミュニケーションスキルの向上
- 人間関係がより円滑になる
- 心の健康維持にも役立つ
1-2. アサーティブでないコミュニケーションとは
アサーティブコミュニケーションを身につけるメリットはご理解いただけたと思いますが、アサーティブではないコミュニケーションはどのような影響をもたらすのでしょうか。典型的な3つのタイプを見てみましょう。
①攻撃型
攻撃型は、自分の意見や感情を遠慮なく主張する タイプです。 言い手はその場ではすっきりするものの、相手への配慮がありません。受け取り手は怒りや不快感を覚え、「もう関わりたくない」という拒絶反応を示したり、沈黙してしまったりします。 このタイプの改善には、自分の感情を客観視し、言いたいことを適切なタイミングやトーンで伝える自己コントロールの習得が欠かせません。
②受け身型
相手と衝突することを極度に恐れ、自分の意見や感情をはっきり伝えられません。 一見「相手を尊重している」ように見えますが、その根底には“自分を守るために相手に合わせる”という自己中心的な動機があります。本来伝えるべき要望や困りごとを飲み込んでしまい、不満や疲労だけが募る悪循環に陥りがちです。
③作為型
ストレートに自己主張せず、露骨な態度や皮肉、嫌味混じりの言動で自分の不満を伝えようとします。 直接的な対立は避けられるものの、相手には「何が言いたいのかわかりにくい」と感じさせます。相手は「気を使わせる相手」「つきあいづらい人」という印象を抱きやすく、結果的に距離を置かれ、信頼関係が築きにくくなります。 意図や感情を適切な言葉とタイミングで伝え、率直かつ配慮あるコミュニケーションを身につける練習が欠かせません。
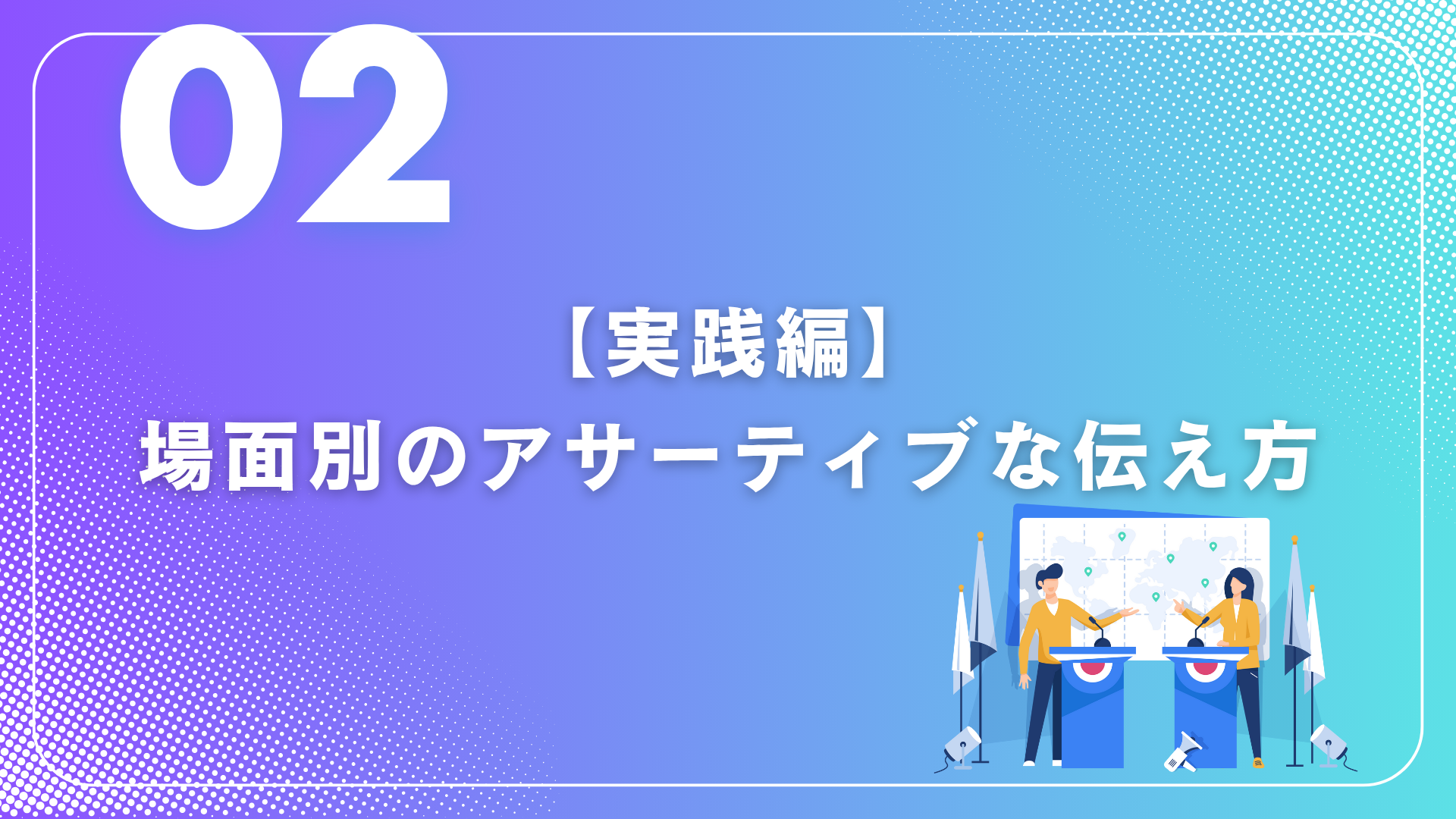
2. 実践編:場面別のアサーティブな伝え方
2-1. まずは自分自身の心の反応のクセを理解しよう
アサーティブを実践するうえで第一歩となるのが、自分の「心の反応パターン」に気づくことです。 たとえば、以下のような反応は、過去の経験や思い込みによって身についた“クセ”かもしれません。
- 「注意されたとき、つい反論してしまう」
- 「頼まれると断れない」
- 「不満を伝えるのが怖い」
このクセを知ることで、「なぜ言いにくいのか?」「なぜ強く言ってしまうのか?」という自分の傾向が見えてきます。
ここで大事なのが、自分自身の性格を変えるのではなく、言い方・伝え方を変えることです。
2-2. 実践に入る前に
アサーティブコミュニケーションは「理論として理解すること」と「実際に使いこなすこと」の間にギャップがあるスキルです。 職場では、上司や部下、取引先、チームメンバーなど立場や関係性の異なる相手とやりとりをする機会が多く、「言い方ひとつ」で伝わり方が大きく変わります。
とはいえ、いざ実践しようとすると、 「これ、どこまで言っていいんだろう?」 「気を使いすぎて逆に伝えられなかった」 「はっきり言ったらきつい印象にならないかな…」 と、迷ってしまうことも少なくありません。
だからこそ、ビジネスシーンに「NG例」とアサーティブな伝え方や考え方を比べながら、ポイントを押さえて実践することが効果的です。
2-3. 意見が対立したとき
自分の意見を主張したいが反対意見を否定せずに伝えるためには、どうすれば良いでしょうか。“違う意見を持っていても、相手を否定せずに伝えることはできる”という前提を持つことが、アサーティブな考え方の第一歩です。
まず初めに、アサーティブでないNG例を見ていきましょう。
NG例:
- 「いや、それは違うと思います。そのやり方は効率悪いですよ」(攻撃型) 意見の内容は正しくても、否定的な印象が強く出てしまい、相手のモチベーションや関係性に悪影響が出やすくなります。
- 「そうですね…(納得していないけど何も言えず黙る)」(受け身型) 自分の視点を共有できず、後から「やっぱりこうすればよかった」と後悔し、チーム内の意思疎通にズレが出る可能性も。
アサーティブな伝え方:
- 「〇〇さんの意見も一理あると思います。そのうえで、私の立場からはこう見えています」
- 「別の視点として、こういう可能性もあるかと思うのですが、いかがでしょうか?」
ポイント: 相手の意見を尊重しつつ、自分の考えを冷静に提示することで、建設的な対話を促すようにしましょう。
2-4. 依頼された仕事を断りたいとき
「断ったら冷たいと思われるかも」「やる気がないって思われそう」そんな風に、無理をしてでも引き受けたり、「忙しいアピールをして察してほしい…」など、はっきり伝えることを避けて、遠回しな態度で断ろうとした経験はないでしょうか。 相手を尊重しながらも、自分の状況や気持ちをきちんと伝えられる“断り方”を身につけておくことが大切です。
NG例:
- 「えっと…たぶん今はちょっと忙しいので…また今度でも大丈夫ですかね…?」(受け身型) 相手にとって「結局できるの?できないの?」と判断しづらく、仕事の進行に支障が出ることも。
- 「あ〜最近すごく忙しくて…(はっきり断らず察してもらおうとする)」 「他の人ならすぐできそうですよね…(遠回しに拒否)」(作為型) 察してほしい気持ちは伝わっても、仕事の調整が進まず信頼やスムーズな連携を損なう場合もあります。
アサーティブな伝え方: 「お声がけありがとうございます。ただ、現在〇〇の業務に集中していて、すぐには対応が難しそうです。〇日以降なら調整できる可能性がありますが、いかがでしょうか?」
ポイント: 断る理由を具体的に伝えつつ、相手の意向を尊重した代替案も提示しているため、関係性を損なうことなく自分の立場を主張できます。2-5. 自分の要望・希望を伝えたいとき
「もっと柔軟な働き方がしたい」「評価について相談したい」など、日々の業務の中で伝えたい希望や思いがある。でも「わがままだと思われたくない」「はっきり言わなくても気づいてほしい…」と、言い出せないままにしていませんか?
NG例:
- 「特に不満はないです(本音:実はちょっと不満ある)」(受け身型) 言わなければ状況は変わりません。不満や希望を押し殺すことで、モチベーションやパフォーマンスの低下につながる恐れもあります。
- 「最近なんだか疲れますね…(遠回しに伝える)」 「みんなはいいですね、自分はずっと残業です」(作為型) はっきり言わないため、相手に真意が伝わらず、かえって気を使わせたり誤解を生む原因になります。
アサーティブな伝え方:
- 「実は、より集中して成果を出すために、週に1日はリモートで働けるようにできないかご相談したくて」
- 「〇〇についての評価が気になっていて、改善のためにアドバイスをいただけたら嬉しいです」
2-6. 実践時の心得:4つの柱
アサーティブコミュニケーションの基本となる「4つの柱(基本姿勢)」は相手との対話において、自分も相手も大切にするというスタンスを支える大切な考え方です。 前述にアサーティブな伝え方の例を挙げましたが、他にも伝え方は何十通りもあります。
しかし、伝え方を覚えるのではなく4つの柱を心に留め、伝えるときの心得にしてみませんか。 それでは、それぞれの柱の意味と特徴を説明します。
①誠実
自分にも相手にも正直でいること。これがアサーティブにおける**“誠実”**の意味です。 言いたいことをぶつけるのではなく、相手の考えを受けとめながら、自分の気持ちも伝えていくバランスが重要です。良いことも、言いづらいことも、誠意を持って相手に伝えてみましょう。嘘偽りなく素直な気持ちを伝えることがアサーティブコミュニケーションに繋がります。
②対等
「立場」や「年次」に関係なく、お互いをひとりの人間としてリスペクトする姿勢が基本です。表面的な言葉遣いよりも、「この人とフェアに会話しよう」という意識が、言葉や態度ににじみ出ます。どちらかが強すぎたり、我慢しすぎたりすると、対話はうまくいきません。 言葉だけでなく、心の姿勢でも「お互いの立場を尊重する」ことを忘れずにしましょう。
③率直
自分の考えや感じていることを、遠回しにせず、素直に言葉にする力です。 ただし、感情をぶつけることとは違います。大切なのは、「私はこう感じています」「私はこう思っています」と、“自分の視点“からシンプルに伝えることが大切です。 誰かの意見に乗っかったり、“正しさ”を押しつけるのではなく、自分の考えを自分の言葉で、ストレートに伝えてみましょう。
④自己責任
うまくいかなかったとき、他人や外部に原因を求めたくなることもあるかもしれません。 しかし、「伝えなかったのも自分の選択」「こう言ったのも自分の意志」と捉えることで、次にどう行動するかが見えてきます。 自分の発言や態度に責任を持つことは、日々のコミュニケーションをより前向きで建設的なものにしていく土台となります。
4つの柱を行動、心の姿勢の指針にしながら、自分らしいアサーティブなコミュニケーションを築いていきましょう。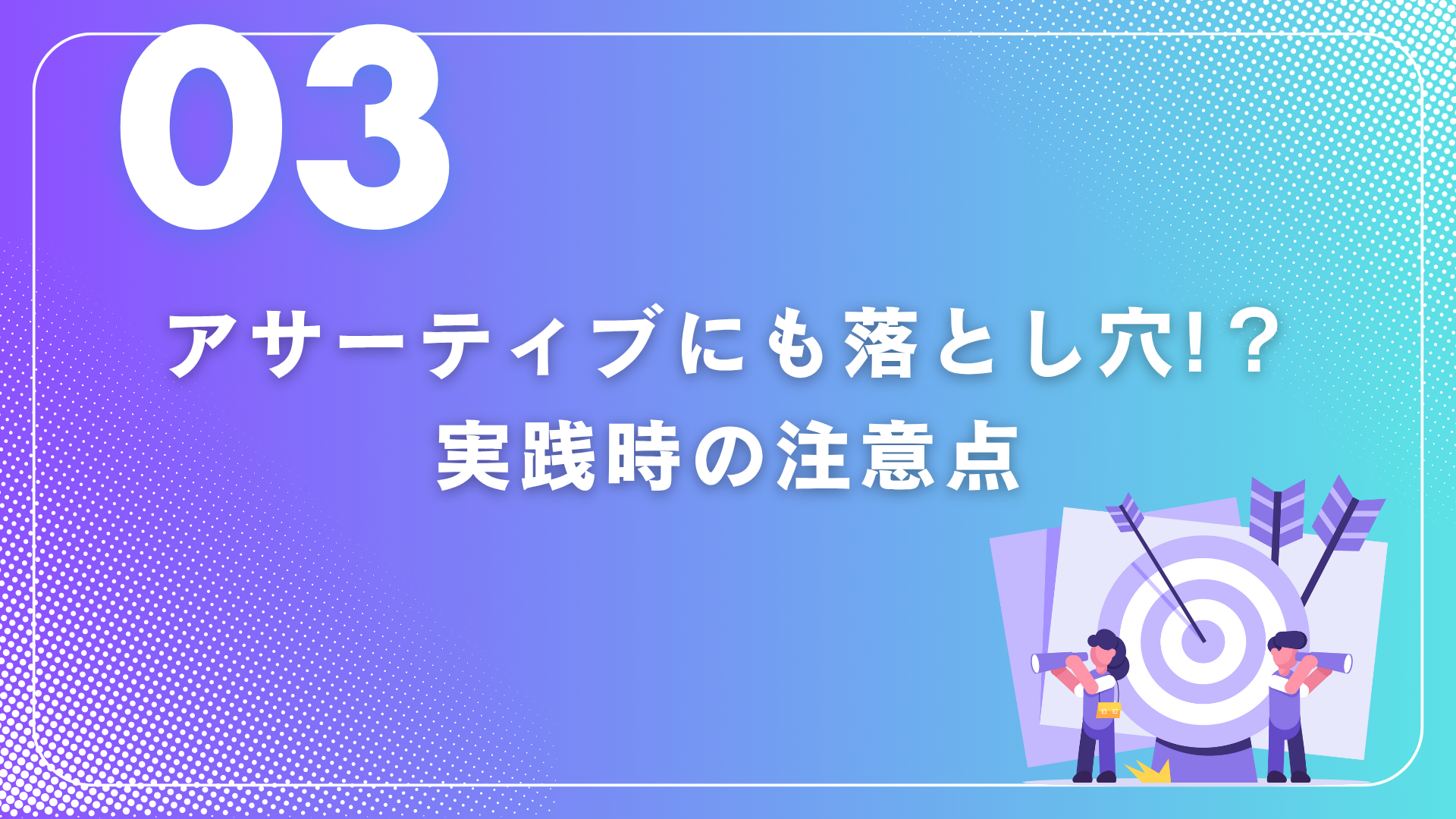
3. アサーティブにも落とし穴?実践時の注意点
アサーティブコミュニケーションは、理想的な対話のかたちです。けれど、どんなに正しい考え方でも、現実のコミュニケーションでは思わぬズレが起きることもあります。 ここでは、「アサーティブに話したつもりなのに、うまくいかなかった…」という事態を防ぐために、押さえておきたい注意点を紹介します。
3-1. 相手によっては誤解されることがある
“アサーティブに話す=遠慮せず思いを伝えること“ですが、相手によっては「主張が強い」「自己中心的」と受け取られてしまう場合もあります。特に、日頃から控えめな態度が習慣になっている人ほど、急に率直に話すことで、相手が驚いたり戸惑うことがあるでしょう。
「率直さ」に「丁寧さ」や「配慮」を添えるのがポイント。 たとえば、「これは私の考えですが…」「気を悪くされたらごめんなさい」など、前置きをつけることで、相手の受け取り方が柔らかくなります。
3-2. 感情的になっている相手には通じにくい
アサーティブは、「冷静な対話」が前提のスキルです。もし相手が怒っていたり、感情的になっていたりする場面では、どれだけ丁寧に言っても、意図が伝わらないことがあります。
まずは相手の気持ちに寄り添い、「少し落ち着いてから後で話しましょうか」と、一度距離を取ることも必要です。タイミングや状況を見極めることも、アサーティブを実践するうえで重要な力です。
3-3. スキルが未熟なうちは、逆効果になることもある
アサーティブは、「言い方ひとつ」で印象が変わる繊細なコミュニケーションスキル。最初は、「強く言いすぎた」「遠慮しすぎた」など、うまく伝わらないこともあります。思いを伝えることに集中しすぎて、相手の受け取り方への配慮が抜けたり、頭では理解していても、実際のやり取りの中では感情や状況が絡むため、理想どおりにはいかないのが自然なことです。
重要なのは、完璧を求めず、実践しながら学ぶ姿勢。「伝えてみる → 反応を見る → 振り返る → 改善する」というサイクルを繰り返す中で、自分らしいアサーティブなコミュニケーションスタイルが育っていきます。うまくいかない経験も、すべてが「練習の一部」になるので、焦らず「伝えたい」という気持ちを持ち続けることが何より大切です。
3-4. アサーティブの「落とし穴」から抜け出すコツ
もし「アサーティブに伝えたはずなのに、うまくいかない…」と感じたら、以下の3つの視点で振り返ってみましょう。
- 視点1:伝え方に偏っていないか。 → 優しさを装って、率直さや誠実さが抜けていないかを確認してみましょう。
- 視点2:相手の立場を想像できているか。 → 自分の「言いたいこと」ばかりに集中して、相手の受け取り方に無頓着になっていないかを振り返りましょう。
- 視点3:本来の目的を見失っていないか。 → アサーティブの目的は「相手を尊重しつつ自分の意見を主張する」こと。勝つことや、思い通りに動かすことではありません。
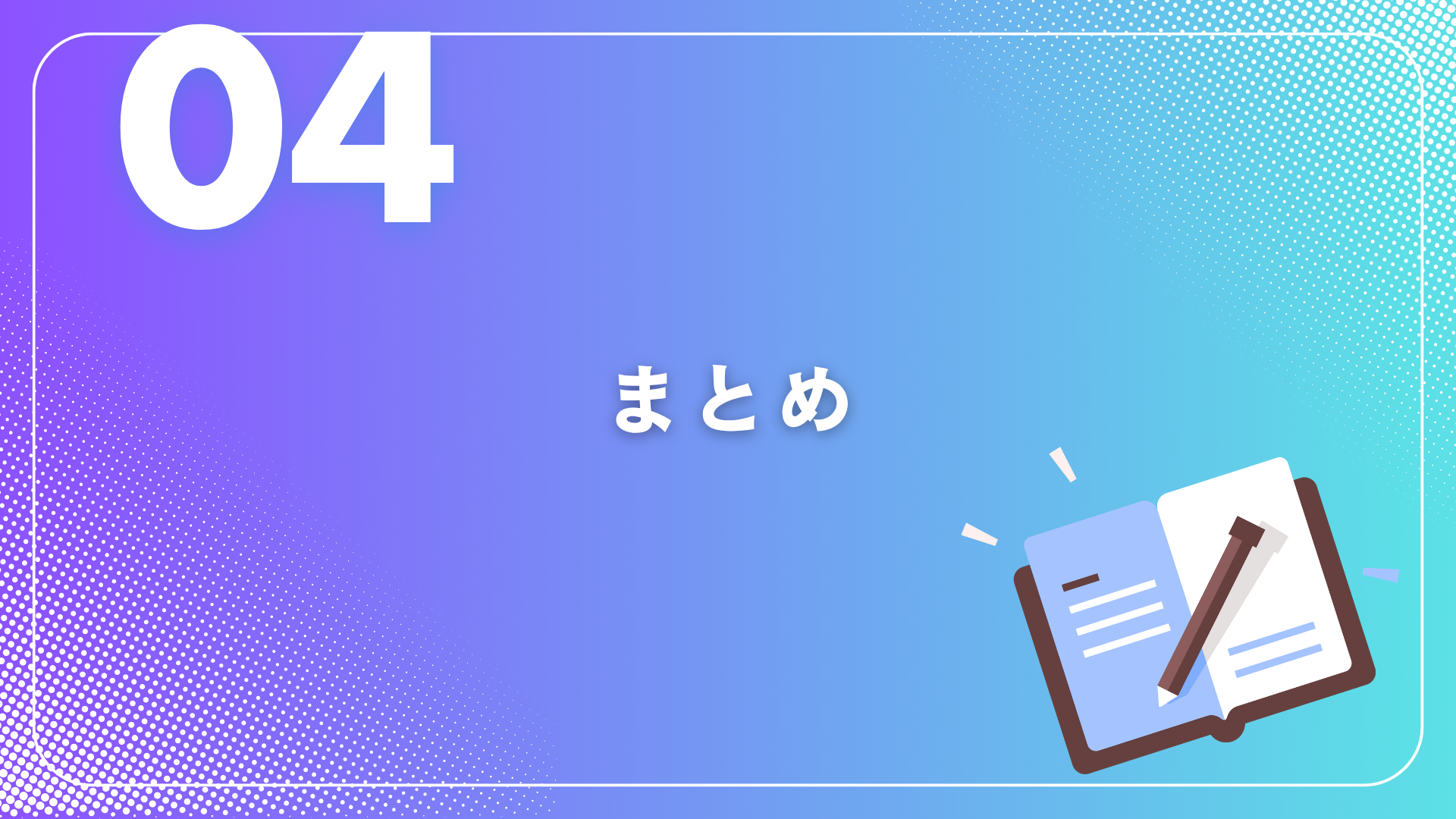
4. まとめ
アサーティブコミュニケーションは、「自分も相手も大切にする伝え方」です。完璧を目指す必要はありません。時には失敗したり、誤解されたりすることもあるでしょう。しかし、そこで「余計な一言だったかな?」「やっぱり言わない方がいい」と黙ってしまうのではなく、「どうしたらもっと伝わるかな?」と前向きに見直していくことが、アサーティブなコミュニケーションを育てる一歩です。
あなた自身の思いを大切にしながら、相手との信頼関係も育てていく。そのための土台が、アサーティブという考え方です。
性格や考え方を根本から変える必要はありません。練習を重ねることで身につくスキルですから、コミュニケーションの方法は自分次第で改善できる、という点をぜひ心に留めておいてください。
焦らず、少しずつ、一緒に実践していきましょう。

